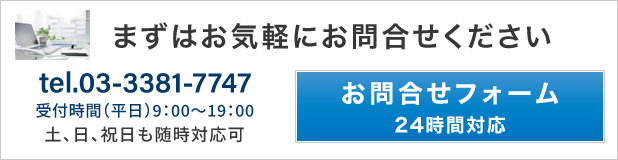遺言・相続のよくある質問
Q.自分で、役所に通い戸籍などを集めてみたけれど、そもそもこれで合っているの?
A.役所は、基本的に申告された通りに機械的にしか書類を発行しません。合っているとは限りません。
役所の記載ミスで、そもそも本籍地が誤記により繋がっていなかった。続柄・生年月日がいつの間にか変わっていた(役所は気づいていない)。戸籍が保存期間を過ぎており発行できないと言われた。
これらは、実際にあった事例です。当事務所にご依頼いただければ、正確な調査は当然の事、役所との折衝により確実な戸籍収集が可能です。
Q.相続財産の不動産って、どうすればわかるの?
A. 固定資産納税通知書に書いてあるよ、と言われることがあると思います。
しかし、固定資産納税通知書には非課税不動産、例えば私道や墓地、山林が記載されていないことが多いです。
当事務所では、特に地方の方には「名寄帳の写し」をお勧めしております。
財産調査を失敗することで、曾祖父名義の田んぼが残っていた、といった事案が起こる可能性が高まってします。ご注意ください。
Q.遺言で一部除外した子供がいる。遺留分という言葉を聞いたことがあるけれど、何か影響はあるの?
A.基本的に、遺言の内容が最優先されます。
ただし、民法では遺留分というものが認められており、これは相続人が最低限もらえる相続分です(父母、配偶者、子についてのみ)。
万が一、相手が遺留分を主張した場合は、遺言によってもこれを避けることはできません。
Q.遺言書を書こうと思うのだけど、息子や娘に相談しながら作ったほうがいいですよね?
A.ご相談されるか否かは自由です。
しかし、専門家としての意見は「相談しないほうがいい」です。
遺言は、あなたの意思であり、想いです。
近親者に相談すると十中八九、相談された側は、自分に財産を残して欲しい方向へ動きます。
それが、遺言を残すことすらためらうことに繋がる傾向があります。
Q.家族が亡くなり、役所への亡くなった届出はしたけれど、これだけでいいの?
A.いいえ、その他にも多くの手続きがございます。
例えば、不動産があれば相続登記を、自動車があれば名義変更を、事業をされているのであれば、役員変更や許認可先の役所へ届出も必要です。
相続税の申告が必要であれば税務署への申告、また、銀行口座や株式の名義変更なども必要となります。